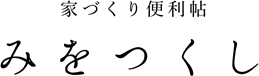INDEX

1.「建築基準法」では、最適ではなく最低の基準を定めています。
日本では建築基準法に従い建物を建てるのが大原則です。その第1条(目的)の条文を、抜粋します。
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
ここには、「最低の基準を定める」と記しています。「最適」ではありません。つまり「この法律には最低の基準を書いていますのでこれを守れば罰則はないですよ、建物の強さ(つまり構造設計)についても、建物をさらに強靭にしたい場合は、建主と施工者で決めて下さいね。」ということです。
では、大地震に対する建築基準法レベルの建物が耐えられる強度とは、どれくらいなのでしょうか? 気象庁震度階に照らし合わせた、その目安を見てみましょう。
建築基準法レベルの耐震強度
震度6強から7程度に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊(ないし崩壊)はしない。
これが、建築基準法レベルの耐震性能である耐震等級1で規定している耐震性の目安です。(国交省、性能表示制度の解説の記載から抜粋。)
言い換えるとこういうことです。
建築基準法レベルの建物の場合、震度5強程度までの地震では、建物のどの部分も壊れる事はほとんどなく、地震後、補修の必要はほぼ無しで生活ができます。
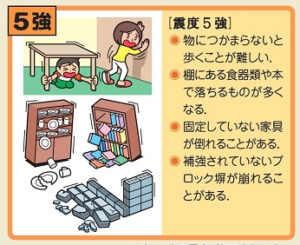
(「気象庁震度階級の解説」資料より抜粋。以下同じ。)
一方で、震度6強から7程度の地震であれば、建物は壊れます。ただし、建物の中の人が圧死するほどの壊れ方はしません。そして、地震後は補修の必要があるし、場合によっては補修が不可能で住めないほどに、壊れる事もあります。

震度6弱の場合、耐震性の高い建物でも、壁や窓ガラスが破損したり落下したりする。とあります。

以上をまとめると、建築基準法レベルの建物の場合、地震前後で全く変化が無いのは、震度5強までと言えるでしょう。
ただし、単純に震度が大きいから建物が壊れるということではありません。2008年7月の岩手県沿岸北部を震源とするM6.8の強い地震は、震度6強の地震だったにもかかわらず、全半壊の家屋がありませんでした。激しい揺れを観測した地域での被害が、地震の規模の割に少なかったのです。
その理由は、「地震波の周期」にありますが、これについては改めてお伝えしたいと思います。

2.建物に損傷を与える規模の地震は、毎年のように発生しています。
私たちは、地震発生直後に各地の震度がニュースで把握できます。気象庁その他の機関が全国に設置した震度計から得られるデータを基に、各地の震度が分かるのです。(その数、約4,000程にもなるそうです)
震度計では、観測された周期、加速度、揺れの継続時間が得られます。これらの観測数値を、所定の計算式に当てはめて得られた数字を計測震度と言います。
地震情報などで発表される震度は、この計測震度から換算されるものなのです。気象庁震度階は、1995年の兵庫県南部地震の翌年の1996年に定められたもので、震度0から、7までの10段階の震度階になっています。
それでは、近年ではどれくらいの規模の地震がどれくらいの頻度で発生しているのでしょうか。
気象庁がまとめている過去の大地震の最大震度と建物被害の数が、こちらの気象庁ウェブサイトで見る事が出来ます。これによれば、震度6弱以上、つまり建物の構造に深刻なダメージを与えるレベルの地震は、全国でほぼ毎年発生しているのが分かります。
3.過去の大地震で損害を受けた住居の数。
この公表データによれば、最大震度7の東日本大震災では、
住家全壊 121,783棟
住家半壊 280,965棟
住家一部破損 745,162棟
と、114万以上の数の住家が被害を受けています。
震度6弱以上を観測した県は、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉と大変広範囲となっています。
最大震度7の、平成28年熊本地震でも、20万戸前後の住家が影響を受けています。熊本地震では震度6弱を上回る地震が計7回観測されました。
当然被害家屋には、耐震強度が低い古家が数多く含まれてはいますが、震度6弱以上の地震が毎年の様に発生していることを考えると、建築基準法レベルの強度で安心とは言い難いでしょう。

4.不確実性の高い地震の影響 - 熊本地震の例。
2016年4月の熊本地震で、最新の耐震基準の住宅が倒壊したという事態が発生しました。1回目の地震で建物の一部が損傷し耐震強度が弱くなったところに、2回目の地震に襲われ倒壊したというのがそのメカニズムです。その二つの地震はいずれも最大震度が7の巨大地震でした。
倒壊した住宅の中には、ハウスメーカーの住宅も含まれていた様で、最新の耐震基準でも絶対はないという実例が発生してしまいました。
専門家の実態調査では、倒壊した家屋が接合部の仕様が不良だったことや地盤が軟弱だったことが指摘されています。
この結果、最低の基準ではもはや物足らないという通念が、最近では出来上がりつつあります。
熊本地震の建築被害調査委員会の報告書によれば、
大きな被害のあった益城町中心部においても、住宅性能表示制度に基づく耐震等級Ⅲの建物には、大きな損傷が見られず、大部分が無被害であった。
とあります。益城町は、震度7の地震が2回発生した地域です。
震度7でも倒壊を許さない建築基準法レベル(つまり耐震等級Ⅰの)建物が倒壊し、一方で耐震等級Ⅲの建物の大部分が無被害であった事実を踏まえると、やはり建築基準法を守っているから安心とは言い難いですね。

5.「法律を守っているから安心」ではありません。
建物の強度を落とせば落とすほど原価を下げることができますので、経済性を優先し、法律で定める最低のギリギリの強度で建物を建てる施工者も存在します。
ただそれが将来の不確実な地震に対して危険かどうかについては、何とも言えません。発生する地震の強度(加速度)や、周期、継続時間次第で建物が受ける被害は変わります。更には地盤の状態にも左右されます。
断言できるのは、耐震強度を強くすればするほど、倒壊や損傷のリスクは下げられるということだけです。
更に言えば、木造住宅の場合、構造材や耐震壁などの劣化に配慮した、耐久性の高い施工をしているかどうかも問われます。新築時には設計通りの耐震性能を確保していても、将来耐久性が劣れば、耐震性も大幅に落ちてしまうのです。
木造住宅の構造設計は、今の法制度の実態を踏まえ、過去の被害から何を学びどんな価値観に従い進めるかという点が問われます。単に法律を守っているというだけでは、余りにも不確かであり、将来にわたっての安全と安心を確実にすることはできません。特に、建物の劣化に伴う、耐震性の低減への対策が欠けると尚更でしょう。

6.まとめ。耐震構造には、劣化対策と誠実な施工が必要条件。
建築基準法レベルの木造住宅の耐震強度をまとめると次のとおりとなります。
東日本大震災では広範囲で震度6弱が観測され、住家一部破損も含むと100万戸以上の家屋が影響を受けました。熊本地震では、震度7クラスの地震が連続したこともあり、建築基準法レベルの建物も倒壊しました。
結論を言えば、建築基準法レベルの構造(=耐震等級Ⅰ)であれば、毎年の様にある震度6弱以上の揺れには無傷では済まないので、更に強くしておくべきであると思います。
また、熊本地震の被災家屋の実態調査によれば、接合部の施工不良で耐震性が確保できていなかった事例、築年数が経過して木材の劣化により耐震性が劣っていた事例などの報告があります。
従って、長期間の耐震性を確保するためには、設計段階での耐震性の確保と、木材の劣化対策に配慮した建て方の両者が必要条件であると言えます。
木材の劣化対策、つまり建物の耐久性については、改めてお伝えしたいと思います。
参考リンク